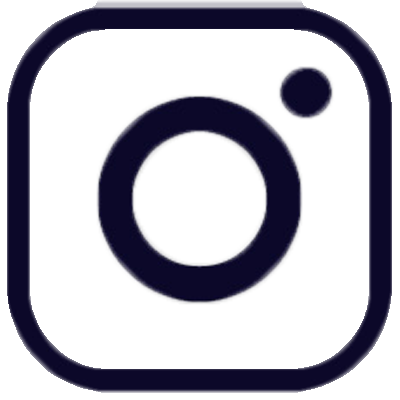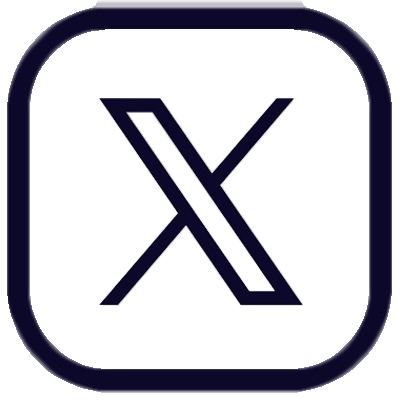お役立ち情報
2025.09.30
助産学校の入試で出た小論文のお題(18)『分娩空白市町村について(800字)』

助産学校の入試で出た小論文のお題(18)
⁻『分娩空白市町村について(800字)』
少子化と医療資源の偏在が重なり、妊婦が自分の住む市町村内で出産できない「分娩空白市町村」が各地で増えています。
背景には、24時間体制の分娩を支える医師・助産師の確保難、産科の採算性の低さ、医療安全を担保するための集約化など、病院を取り巻く厳しい現実があります。結果として、妊婦が長距離を移動して周産期センターに通院・出産するケースが増え、交通費や宿泊費、家族ケアの負担がのしかかります。自治体や国は支援策を打ち出し始めましたが、過疎地域では医療機関の撤退が相次ぎ、危機感が高まっています。
本稿では、分娩空白市町村の定義と現状、具体例、課題と対策を整理し、助産師を志す立場から小論文でどう論じるかの道筋を示します。
| ●分娩空白市町村とは(定義と背景) |
分娩空白市町村とは、市町村の区域内に「分娩を取り扱う医療機関(産科のある病院・診療所、助産所など)」が存在せず、妊婦が区域外へ移動して出産せざるを得ない自治体を指します。近年、産科の集約化や人材不足でこの“空白”が拡がっています。たとえば鹿児島県南さつま市では、唯一の産婦人科医院が閉院し、市内での分娩が不可能となりました。妊婦は隣接市の病院へ通わざるを得ず、移動の負担が増しています。地域の医療資源が限られるなか、分娩の安全確保を優先した集約化が進む一方、生活者側には時間的・経済的負担、夜間の急変時対応のリスクが生じます。
こうした現実は、地方だけでなく都市近郊でも起こり得る構造的な課題と言えます。
| ●出題者の意図 |
このテーマの狙いは、
(1)妊産婦の安全と権利をどう守るかという視点
(2)医療提供体制の持続可能性という現実
(3)助産師として当事者に寄り添いながら現実的な解決策を提示できるか
を同時に評価する点にあります。
データや実例を踏まえつつ、「誰が・何を・どうやって」支えるかを具体化できるかが問われます。
単なる制度批判や理想論ではなく、
①搬送・待機宿泊の支援、②地域連携(周産期センター、基幹病院、助産所、行政、保健師)、③妊婦教育とバースプランの再設計、④ICT/遠隔助言の活用、⑤医療者確保と働き方改革など、
複数レイヤーの提案を接続して論じられると評価が上がります。
| ●現状と課題(地域格差・閉鎖の連鎖) |
現場では、医師の偏在・高齢化や勤務負担の重さから分娩取扱いの休止・閉鎖が相次いでいます。産科を継続するには、24時間オンコールや麻酔・小児科との連携、助産師確保など相当のコストが必要で、採算面の厳しさが撤退を促す悪循環になっています。
三重県でも分娩取扱いのない地域が生じ、住民は1時間以上の移動を強いられる例が報じられました。国は遠方出産に伴う交通・宿泊費の助成を進めていますが、制度だけでは移動負担や夜間の急変リスクをゼロにはできません。また、婦人科は存続しても分娩だけをやめる医療機関が増え、地域の“妊娠~出産~産後”の切れ目が生じやすくなっています。
こうした空白をどう埋めるかが、妊産婦の安心と周産期医療の持続可能性に直結します。
| ●どう書くか(800字構成のコツ) |
①導入:
「分娩空白市町村」とは何かを端的に定義し、最近の報道例を1つ挙げて問題の実在感を出す。
(例:鹿児島県南さつま市の事例)
②背景:
医師・助産師不足、24時間体制の負担、医療安全の観点からの集約化、採算性の問題、災害や悪天候時のリスク増などを整理。
③影響と提案:
通院・付き添い・待機宿泊・育児家族の調整・救急搬送の遅延など具体的に。
〈短期〉移動・宿泊の公的助成、妊婦への個別避難計画、オンライン助言、救急連携の強化。
〈中長期〉地域助産所/院内助産の活用、ハイリスクは集約・ローリスクは地域でのハイブリッド、広域連携MOU、人材確保と働き方改革。
④結論:
「安全と選択肢の両立」を掲げ、助産師として伴走する決意で締める。
厚労省の周産期医療体制や助成に触れつつ、地域の実情に即した現実解を示すと説得力が増します。
| ●まとめ |
分娩空白市町村の拡大は、単なる「病院がない」問題ではなく、地域に住む妊婦・家族の移動、費用、安心感、そして緊急時の安全性に直結する生活課題です。
報道が示すとおり、閉院・撤退は現実に起きており、過疎地域を中心に危機感は強まっています。だからこそ、短期の負担軽減(交通・宿泊支援、オンライン支援、搬送体制)と、中長期の体制づくり(助産所の活用、院内助産・助産外来の強化、人材確保、広域連携)を並走させる必要があります。助産師志望者は、妊婦の意思決定を支え、産前から産後までの切れ目ない支援を設計できる専門職です。
小論文では、データと実例を踏まえ、「安全と選択の両立」という軸で、地域に根ざした現実解を示すことが合格への鍵となるでしょう。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール