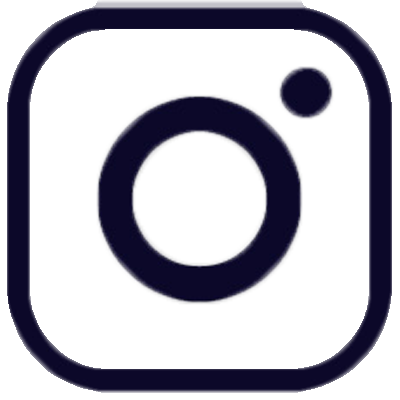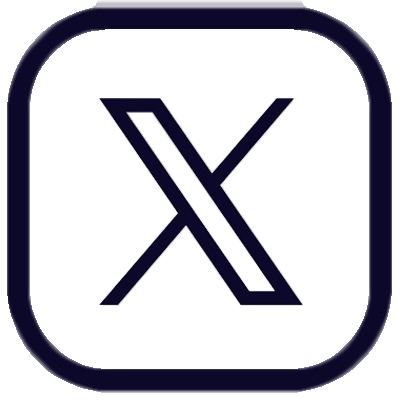お役立ち情報
2025.08.16
看護大学・看護学校の入試で出た小論文・作文のお題 (43)『”大丈夫”という言葉についてあなたはどう考えますか?(800字・60分)』

看護大学・看護学校の入試で出た小論文・作文のお題 (43)
⁻『”大丈夫”という言葉についてあなたはどう考えますか?(800字・60分)』
「大丈夫」という言葉は、日常生活の中で誰もが使うありふれた言葉です。しかし、その一言には多くの意味や背景が込められています。例えば、友人が怪我をして「大丈夫」と答える時、本当に大丈夫である場合もあれば、心配をかけまいとする「やせ我慢」の場合もあります。また、誰かを励ます時や安心させるために「大丈夫だよ」と声をかけることもあります。このように「大丈夫」は、場面や使い手の気持ちによってニュアンスが変化する多面的な言葉なのです。
入試において「大丈夫」という言葉をテーマに問われるのは、この一見シンプルな言葉の裏側にある心理や人間関係を掘り下げて考える力を試されているからです。医療職を志す者としては、患者さんが口にする「大丈夫」という言葉をどう受け止め、どう寄り添うかが問われています。看護師や助産師は、相手の小さな言葉の裏にある「本当の声」を汲み取る必要があるからです。
このブログでは、「大丈夫」という言葉の意味や使われ方、そこから導き出せる医療職としての姿勢について掘り下げていきます。さらに、出題者が何を意図してこのお題を出しているのか、どのように書けば評価されるのかを整理し、最後にまとめを提示します。小論文を書く上での参考にしてください。
| ●「大丈夫」という言葉の多面性 |
「大丈夫」という言葉は、日本語の中でも特に便利で頻繁に使われる表現です。しかし、その意味は一様ではなく、以下のようにいくつもの側面を持っています。
・安心を与える「大丈夫」…相手を励まし、前向きな気持ちにさせる。
・強がりの「大丈夫」…本当は苦しいのに、心配をかけまいと自分を押し殺して発する。
・確認の「大丈夫?」…相手を気遣い、状態を把握しようとする問いかけ。
・自己暗示の「大丈夫」…自分自身を落ち着かせ、勇気を出すための言葉。
このように、一言で「大丈夫」と言っても、その裏にある心理はまったく異なることが多いのです。特に医療現場では、患者さんが「大丈夫」と答える時、それをそのまま受け取るのではなく、背景にある不安や我慢を読み取る力が求められます。
| ●出題者の意図 |
このお題を通して出題者が評価したいのは、表面的な言葉を超えて人の気持ちを想像し、掘り下げて考えられる力です。医療職にとって、患者の言葉の奥にある感情やニーズを汲み取ることは非常に重要です。
例えば、怪我をした人が「大丈夫です」と言った時、本当に大丈夫なのか、それとも周囲に迷惑をかけまいとする気遣いなのか。そこを見極めることは、患者安全や信頼関係の構築に直結します。また、「大丈夫だよ」と声をかけることで、相手の不安を和らげる力があることにも気付いてほしい、という意図もあるでしょう。
つまり、「大丈夫」という言葉をどう捉えるかは、あなたが人と関わる時にどれだけ深く寄り添えるかを示す試金石でもあるのです。
| ●どう書くか |
小論文でこのテーマに取り組む際は、以下の流れで書くと効果的です。
①「大丈夫」という言葉の一般的な意味を整理する
② 強がりややせ我慢として使われる場面を挙げ、言葉の裏にある心理を考察する
③ 励ましや安心を与える前向きな使い方について触れる
④ 医療職として「大丈夫」という言葉をどう受け止め、どう行動すべきかを述べる
特に重要なのは④です。患者さんが「大丈夫」と言っても、それを鵜呑みにせず観察を続けること、あるいは「大丈夫だよ」と声をかけて安心を与えること。両方の側面から述べると説得力が増します。
また、日常生活のエピソードを交えると読みやすくなります。例えば「友人が熱を出したのに『大丈夫』と言って部活に来て、結果的に悪化してしまった」というような体験談は、言葉の限界を示す具体例として効果的です。
結論では、医療職を目指す自分自身として「相手の『大丈夫』を信じすぎず、寄り添って本当の気持ちを引き出せる看護師になりたい」といった抱負を盛り込むとよいでしょう。
| ●まとめ |
「大丈夫」という言葉は、単純でありながら非常に奥深い言葉です。その裏には強がり、不安、安心、励ましといった様々な感情が潜んでいます。小論文でこのテーマが出題されるのは、言葉の奥にある人間心理をどれだけ洞察できるかを測るためです。
医療職としては、患者さんの「大丈夫」を表面だけで受け止めず、観察と対話を通して本音を理解することが求められます。そして同時に、自分から「大丈夫」と声をかけて安心を与える姿勢も大切です。
入試でこのテーマが出た時は、「大丈夫」という言葉の両義性を整理し、医療者としてどう向き合うべきかをしっかり書くことで、あなたの考察力と人間理解力をアピールできるでしょう。
最後にひとこと。もしこのテーマについて考え、入学を目指すあなたが「大丈夫」と口にするなら、それは「きっと合格できる、大丈夫!」という前向きな意味であってほしいと思います。入学したら、遅刻せず元気に頑張ってくださいね!
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール