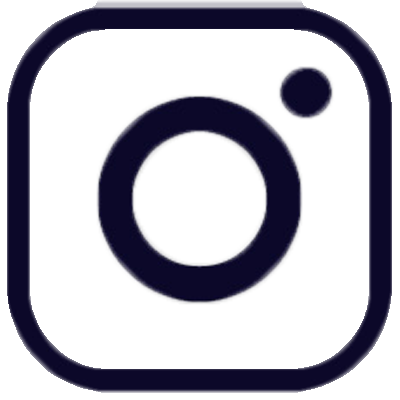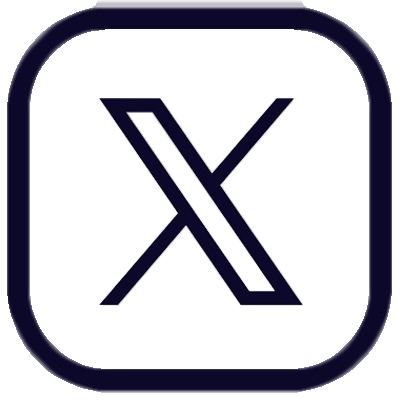お役立ち情報
2025.08.09
看護大学・看護学校の入試の面接で聞かれた内容(35)『この学校がつくられた理由を知っていますか?』

看護大学・看護学校の入試の面接で聞かれた内容(35)
⁻『この学校がつくられた理由を知っていますか?』
看護学校や看護大学の面接で、意外に多く聞かれるのが「この学校がつくられた理由を知っていますか?」という質問です。一見すると雑談のようにも聞こえますが、実は受験生の「志望校理解度」や「入学後の定着度」を測る大切な問いです。
看護系の学校は、単に学びの場として存在しているわけではなく、設立当初から明確な目的や地域医療への使命を持っています。たとえば、地方の医療格差を埋めるための人材育成、特定病院や医師会が必要とする看護師確保、企業が自社病院の人材を育てる福利厚生策など、背景はさまざまです。中には「卒業後は一定期間、地域内や附属病院に勤務する」という条件付きの学校も存在します。
こうした設立理由を知っているかどうかは、その学校への本気度を示すバロメーターでもあります。面接前には、パンフレットや学校案内だけでなく、公式サイトや設立時の資料、地域ニュースなどもチェックし、背景を自分の言葉で説明できるよう準備しておきましょう。
| ●看護学校の設立背景と種類 |
看護学校や看護大学の設立には、大きく分けていくつかの背景があります。まず多いのは「地域医療に貢献する人材の育成」という目的です。医師不足・看護師不足が深刻な地域では、地元出身者を育て、地域での就職・定着を促すために学校が設立されることがあります。
次に多いのが、病院や医師会が設立するケースです。病院附属看護学校では、その病院で働くことを前提に教育を行い、即戦力として現場に送り出すことが目的です。また、医師会立や県病院協会立の学校は、地域の複数病院が共同で必要な看護師を確保するために運営されます。
さらに、かつては企業の福利厚生として設立された例もあります。大手企業が自社運営の病院や健康管理施設を持ち、その職員を養成するために看護学校を併設したのです。
こうした学校の中には、「卒業後○年間は必ずこの地域や関連病院で勤務する」という条件を設けている場合もあります。これは地域の医療体制を守るための仕組みであり、奨学金制度や学費免除とセットになっていることも少なくありません。受験生は、志望校がどのような背景で生まれたのかを調べることで、面接時に具体的かつ熱意ある回答ができるようになります。
| ●面接官の意図 |
面接官がこの質問をする背景には、いくつかの意図があります。第一に、「志望校への理解度と熱意」を測るためです。学校の設立理由を知らない場合、「受験校の情報収集をしていない」「入学後すぐ辞めてしまうかもしれない」という印象を持たれる可能性があります。
第二に、「学校の理念と自分の目標が合っているか」を確認するためです。たとえば、地域医療への貢献を目的とした学校に対し、「都会の病院でキャリアを積みたい」とだけ話すと、ミスマッチと判断されかねません。
第三に、「将来の定着可能性」を探る狙いです。特に附属病院や地域就業義務がある学校では、卒業後にその場所で働けるかが重要です。面接官はその覚悟を確認し、入学後の離脱リスクを減らそうとしています。
つまり、この質問は単なる知識確認ではなく、「学校理念への共感度」「地域・職場への適応可能性」「入学後の継続意欲」を同時に見ているのです。
| ●どう答えるか |
答えるときは、まず事実を簡潔に述べ、その上で自分の思いや結びつけを話すのがポイントです。たとえば、
「この学校は昭和40年代に地域医療に貢献できる看護師を育成するために、県病院協会によって設立されたと伺っています。私は地元での医療活動に携わりたいという気持ちがあり、この理念に共感しました」
といった形です。
また、附属病院や地域就業義務がある場合には、
「卒業後は○○病院で勤務することが前提ということも理解しています。そのために今から地域医療についての理解を深めています」
と具体的な行動意欲を示すと良いでしょう。
重要なのは、「知識+共感+行動意欲」の3点セットです。パンフレットやホームページで調べた内容をそのまま暗記するのではなく、「だから私はこの学校を選びたい」という理由を添えることで、説得力が格段に増します。
| ●まとめ |
「この学校がつくられた理由を知っていますか?」という質問は、志望校研究の深さを測る試金石です。学校の設立背景には、地域医療への貢献、人材確保、企業の福利厚生など、多様な目的があります。受験生は、志望校の成り立ちを理解し、その理念と自分の目標を結びつけて語れるよう準備しましょう。
こうした下調べは、面接だけでなく志望理由書や将来設計にも直結します。入学後は、設立の背景を胸に刻み、地域や現場で求められる看護師として成長していくことが期待されています。
✅ 学校研究のポイントまとめ(3箇条)
- 学校の設立目的・背景を公式資料や地域ニュースで確認する
- 設立の理念と自分の目標・将来像を関連付けて語れるようにする
- 附属病院や地域就業義務などの特徴も理解し、覚悟を持って臨む
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール