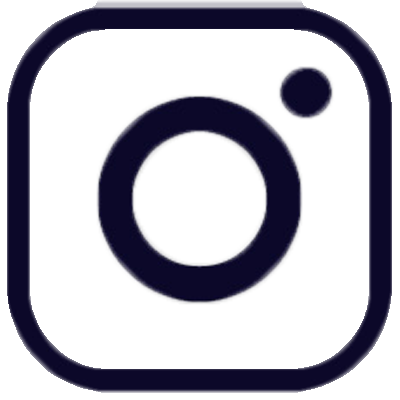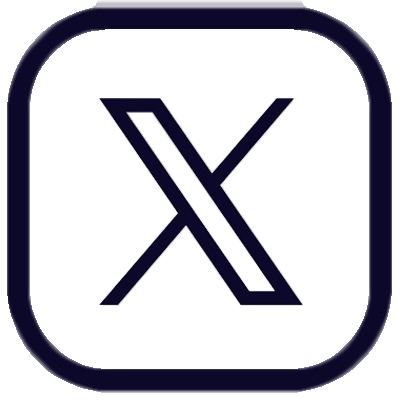お役立ち情報
2025.07.01
看護大学・看護学校の入試のグループ討論で出されたお題(20)『コミュニケ―ションにおいて大切なこととは』
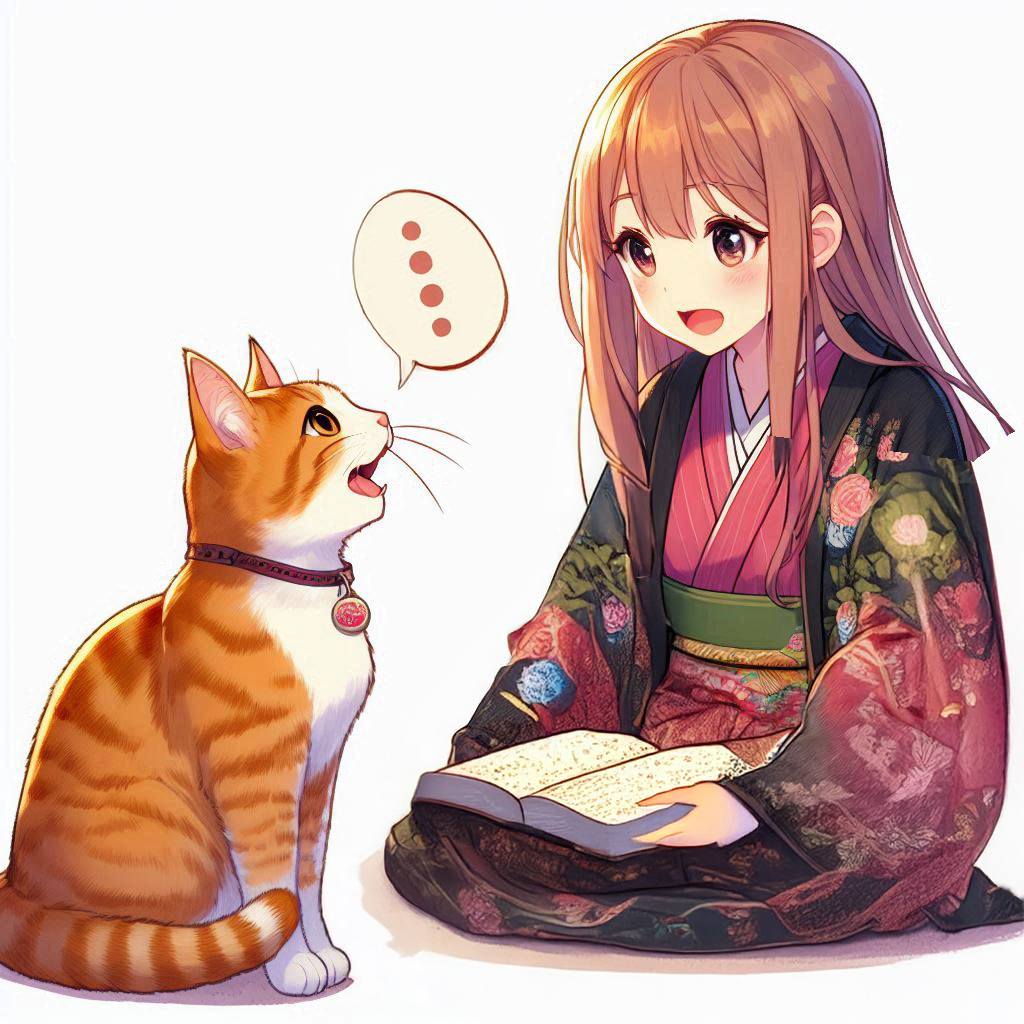
看護大学・看護学校の入試のグループ討論で出されたお題(20)
⁻『コミュニケ―ションにおいて大切なこととは』
看護学校・看護大学の入試では、グループ討論が重視される場合があります。なかでも「コミュニケーションにおいて大切なこととは」というテーマは、過去にも複数の学校で取り上げられており、医療職をめざす受験生にとっては避けて通れない問いです。
医療の現場は多職種連携で成り立っており、患者さんやご家族との信頼関係も「言葉のやりとり」を通じて築かれていきます。つまり、コミュニケーションの力は、看護職者にとって「ケアの土台」といえるほど大切な要素なのです。
この記事では、グループ討論でこのテーマが出題されたときのために、「コミュニケーションの本質」「医療との関係性」「討論の展開例」などを丁寧に解説していきます。
| ●コミュニケーションにおいて何が大切か |
コミュニケーションとは、単に「話す」「聞く」だけではありません。相手の表情や声のトーン、沈黙の意味など、非言語的な要素も含めて、互いに理解しあおうとする行為です。
このテーマで討論する際に意識したいのは、「相手の立場に立つことの大切さ」です。自己中心的な伝え方では、たとえ言葉にしても相手の心に届かないことがあります。
例えば、保育園や飲食店などでの接客アルバイト経験がある人は、「お客様の反応を見ながら臨機応変に対応した経験」などを思い出して話すと、日常的な例として説得力が増します。相手の話をさえぎらずに聞く、気持ちをくみ取る、必要に応じて説明を補うといった配慮が、良いコミュニケーションには不可欠です。
| ●医療職とコミュニケ―ション力 |
医療現場では、患者さんとのコミュニケーションだけでなく、チームメンバーとの情報共有や意思疎通も極めて重要です。
看護師は「患者さんの状態を観察する」「医師や多職種と連携する」「ご家族に説明する」など、さまざまな場面で「伝える」「受け取る」力が求められます。特に高齢者や障がいを持つ患者さんとのやりとりでは、言葉だけでは伝わらないことも多く、柔らかい表情や落ち着いた口調、ゆっくりした説明が必要です。
また、患者さんの「気づきにくい変化」を発見するには、観察と同時にコミュニケーションの力が不可欠です。小さな違和感を感じとる感性もまた、「伝える力」と「受け取る力」の両方を支えています。
| ●試験官の意図 |
このようなテーマを出題する試験官が見ているのは、「知識」よりも「人柄」や「姿勢」です。討論の場面では、単に知っていることを話すよりも、「相手の意見に耳を傾け、自分の意見も丁寧に伝えられるか」が重視されます。
たとえば、他人の話を聞かずに自分の主張ばかり話すようでは、グループワークの資質を問われる可能性があります。「わたしは○○だと思いますが、△△さんのお話を聞いて、別の視点に気づきました」といった柔らかな応答ができれば、好印象を与えるでしょう。
また、「コミュニケーションとは相手との共同作業である」という考え方をもっているかどうかも、試験官は見逃しません。
| ●グループ討論の進め方 |
グループ討論では、進行役(ファシリテーター)を立てる、発言回数を平等に保つ、時間配分に気を配るなど、形式面も大切です。最初に「意見を否定しない」ことを共有し、「結論を出すこと」をゴールに据えてスタートするとスムーズです。
発言は短く簡潔に、他者の意見に補足する、共感を挟む、疑問を投げかける、といったやりとりの工夫が討論を活性化させます。「自分と異なる意見でも、一度は受け止めてみる」姿勢が、グループとしての調和を生み出します。
| ●結論のまとめ方 |
グループ討論の最後には、「討論の成果」を簡潔にまとめることが求められます。たとえば「傾聴」「共感」「状況に応じた対応」「言葉以外の表現(非言語コミュニケーション)」などが重要だという結論に至ったなら、それを一文で表現しましょう。
「私たちのグループでは、コミュニケーションで最も大切なのは 相手の立場に立つ姿勢 であるという結論に至りました」といった簡潔なまとめが有効です。
| ●まとめ |
「コミュニケーションにおいて大切なこととは?」という問いに、唯一の正解はありません。しかし、看護職を目指す人にとっては「相手の立場を尊重すること」「わかりやすく、丁寧に伝えること」「気持ちをくみ取ること」が基本となるでしょう。
グループ討論では、「何を話すか」だけでなく、「どう話すか」も評価されます。協調性と主体性のバランスを意識しながら、あなた自身の経験や考えを言葉にしてみてください。
🎨 挿絵について・・・
猫は人間と意思疎通がしやすい動物ですが、野生の頃はほとんど鳴かず、母猫と子猫の間で鳴く程度でした。それが人間と暮らすうちに「鳴いて伝える」性質が強まったと考えられています。 猫の「ニャー」は、人間の赤ちゃんの泣き声と周波数が似ているため、人間が反応しやすいという説もあります。
猫は 農耕が始まった頃(新石器時代)から、穀物倉庫でネズミ退治をする役目で人間と共存してきました。猫は人間のパートナーになり、今のようなコミュニケーションの上手なペットに進化したといわれています。🙀
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール