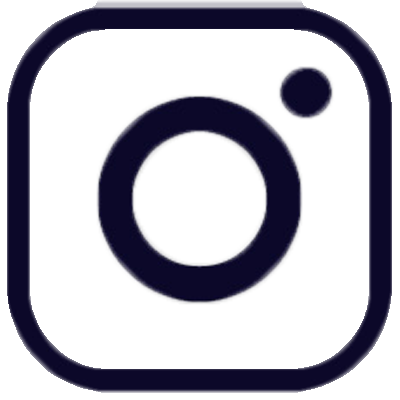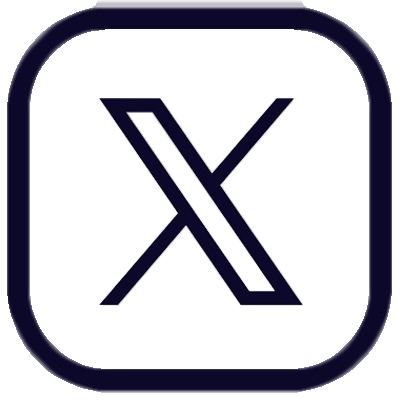お役立ち情報
2025.05.24
看護大学・看護学校の入試のグループ討論で出されたお題(16)『たばこの自動販売機は必要か?(6人で)』

看護大学・看護学校の入試のグループ討論で出されたお題(16)
⁻『たばこの自動販売機は必要か?(6人で)』
看護大学・看護学校の入試におけるグループ討論では、社会的な問題に対する多角的な視点や協調性が求められます。
今回は「たばこの自動販売機は必要か?」というテーマについて、現状の統計や背景を踏まえながら、討論のポイントを整理してみましょう。
| ●喫煙者数の推移 |
日本における喫煙者数は年々減少傾向にあります。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、成人男性の喫煙率は2000年の約50%から2023年には約25.6%に、成人女性の喫煙率も同期間に約15%から約6.9%に減少しています。(※1)
この背景には、健康志向の高まりや禁煙政策の強化、加熱式たばこの普及などが影響しています。
| ●全国のたばこの自動販売機の台数 |
たばこの自動販売機は、かつては全国に広く設置されていましたが、近年その数は大幅に減少しています。日本自動販売システム機械工業会の資料によると、2005年には約62万台あったたばこ自販機は、2022年には約9万2,300台にまで減少しています。(※2)
この減少の要因としては、成人識別ICカード「taspo(タスポ)」の導入や、未成年者の喫煙防止対策、喫煙者数の減少などが挙げられます。
| ●コンビニエンスストアと自動販売機とたばこ店での販売数の対比 |
たばこの販売チャネルは多様化していますが、近年はコンビニエンスストアでの販売が主流となっています。財務省の資料によると、たばこ販売における営業形態の割合は、コンビニエンスストアが約26.7%と最も高く、たばこ専業店が約12.7%となっています。
一方、自動販売機での販売は、前述の通り台数の減少とともにその割合も低下しています。対面販売のたばこ店では、年齢確認や商品説明などが可能であり、未成年者の喫煙防止や適切な情報提供が期待できます。(※3)
| ●試験官は何を見ているか |
グループ討論において、試験官は以下のポイントを重視しています。
・多角的な視点:喫煙者と非喫煙者の立場、健康への影響、経済的側面など、さまざまな観点から意見を述べられるか。
・協調性:他の受験者の意見を尊重し、円滑な議論を進められるか。
・論理的思考:自分の意見を根拠を持って説明し、説得力のある主張ができるか。
・柔軟性:他者の意見を受け入れ、必要に応じて自分の考えを修正できるか。
討論では、単に賛成・反対を述べるだけでなく、具体的な事例やデータを用いて議論を深めることが求められます。
| ●どう答えるか |
このテーマに対して「正解」はありませんが、重要なのは自分の立場を明確にし、論理的に説明することです。討論では以下のような構成で答えると、説得力が増します。
-
立場をはっきりさせる: 最初に立場を述べておくと、議論に軸ができます。
「私は、たばこの自動販売機は段階的に減らしていくべきだと考えます。」
「私は、一定の条件のもとで自動販売機を残すことも選択肢の一つだと思います。」など -
根拠を挙げて説明する: 一方的な主張ではなく、相手の立場も理解しつつ、自分の考えを丁寧に伝える姿勢が大切です。
「喫煙者にとって利便性が下がるという意見も理解できます。だからこそ、すぐに撤去するのではなく、代替手段や段階的な縮小を検討するべきだと思います。」など -
看護・医療職志望としての視点も加える: 看護師・保健師を目指す受験生として、医療職ならではの視点を持っておくと好印象です。
「健康教育の重要性を考えると、未成年者へのアクセスは厳しく制限されるべきだと感じます。」
「患者さんの生活習慣に関わる立場として、たばこの購入環境も含めた社会全体の健康づくりに関心があります。」など
| ●まとめ |
「たばこの自動販売機は必要か?」というテーマは、健康、経済、社会的責任など多くの要素が絡む複雑な問題です。討論に臨む際は、最新の統計や政策動向を把握し、多角的な視点から意見を述べることが重要です。また、他者との協調や柔軟な思考も評価の対象となります。
日頃から社会問題に関心を持ち、情報収集を怠らないようにしましょう。
(※1)国立がん研究センターがん情報サービス ![]()
(※2)日本自動販売機械システム工業会 ![]()
(※3)財務省 令和元年度たばこ小売販売業調査 ![]()
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール