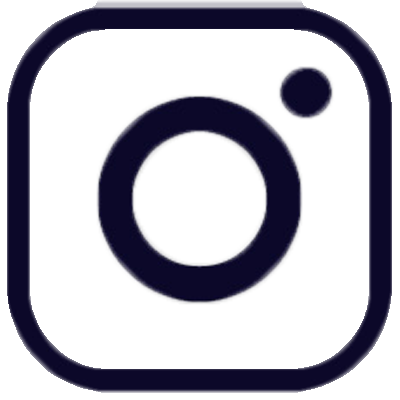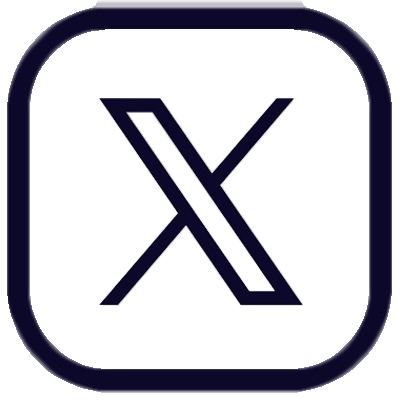お役立ち情報
2025.05.21
助産学校の入試で出た小論文のお題(12)『若年妊婦の看護について(800字)』
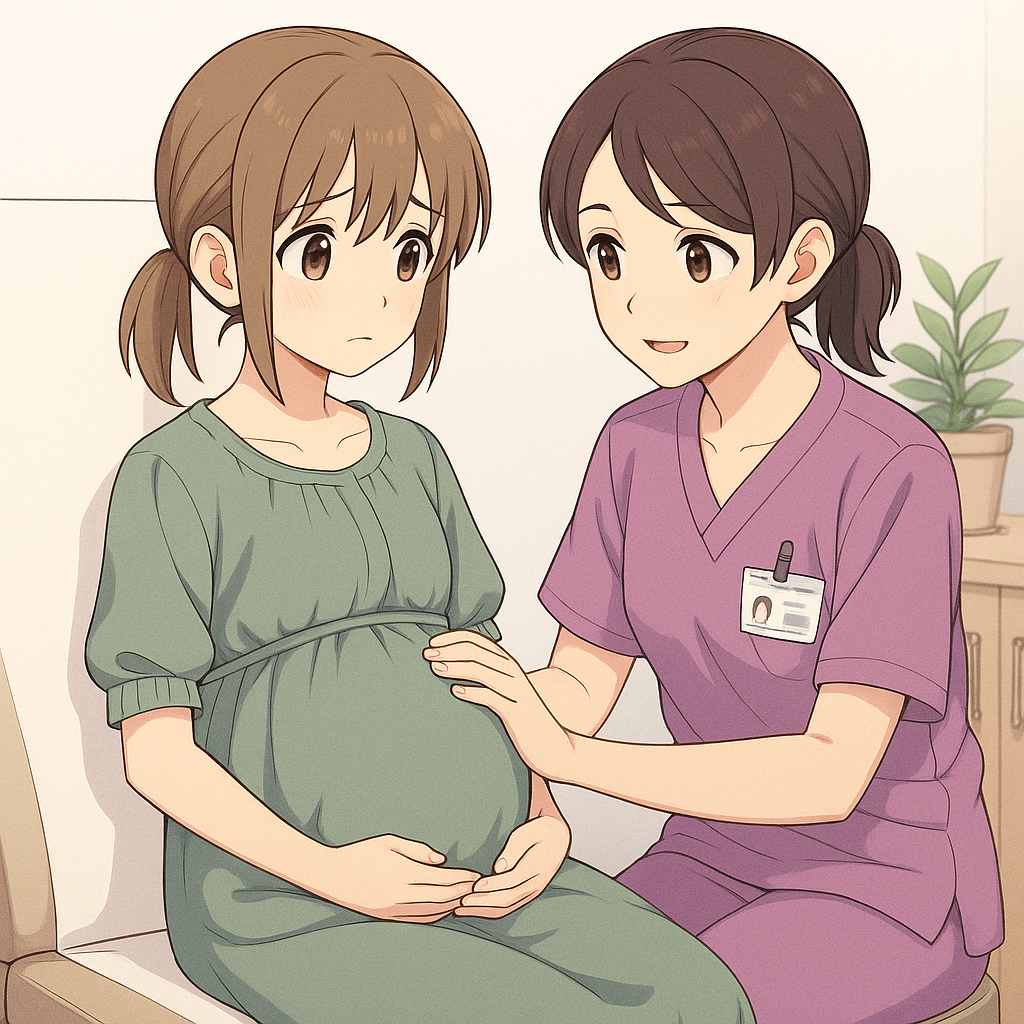
助産学校の入試で出た小論文のお題(12)
⁻『若年妊婦の看護について(800字)』
助産学校の入試では、社会的な背景を踏まえた看護課題に関する小論文が出題されることがよくあります。
今回は実際に出題された「若年妊婦の看護について(800字)」というお題をもとに、若年妊婦の現状、課題、必要な支援、そして小論文を書くうえでのポイントについて解説します。
| ●若年妊婦の現状と問題点 |
「若年妊婦」とは、一般的に10代から20代前半で妊娠・出産を経験する女性を指します。厚生労働省の統計によると、近年は晩婚化が進み、初婚年齢の全国平均は女性で29.7歳(令和4年)となっています。この中で10代や20代前半での妊娠・出産は、相対的に“若年”に分類され、社会的にも特別な支援が必要とされる層です。
若年妊婦が直面する問題は多岐にわたります。まず、年齢が若いために妊娠や出産に関する正しい知識が不足していることが多く、インターネットやSNSなどの不確かな情報に左右されやすい傾向があります。また、若年であるがゆえに周囲の偏見にさらされたり、妊娠したこと自体を周囲に相談できず、孤立しやすいという特徴もあります。 さらに、経済的な基盤が整っていない場合が多く、自立した生活が難しい状況にあります。パートナーからの支援を受けられず、両親に頼らざるを得ないケースも少なくありません。
こうした中で、育児に必要な環境が整わず、精神的にも不安定になりやすいことが、若年妊婦の大きな課題となっています。
| ●どのような支援があるか |
若年妊婦を支えるために、さまざまな支援体制が整えられつつあります。特に重要なのは、「信頼して相談できる環境」があるかどうかです。助産師や保健師、スクールカウンセラーなどが妊婦の話を丁寧に聞き、本人の気持ちや考えを尊重する姿勢が、最初の支援の入り口になります。
家庭内での支援が難しい場合には、自治体の母子保健サービス、母子生活支援施設、NPO法人によるサポートなどを案内することが大切です。例えば、NPO法人「ピッコラーレ」などは、10代や若年の女性の妊娠に関して無料で相談を受け付け、出産後の育児支援にも力を入れています。
また、助産師は妊婦と最も近い立場にある専門職として、彼女たちの気持ちに寄り添う姿勢が欠かせません。相談者に「あなたの話を聞いてくれる人がいる」と思ってもらえるだけでも、精神的な安定につながり、前向きに出産や育児と向き合えるようになります。
| ●小論文を書く際のポイント |
このテーマで小論文を書く際には、以下の構成を意識することが大切です。
①【導入】 若年妊婦とは何か、社会的背景(初婚年齢や晩婚化の傾向など)を簡潔に説明します。
②【問題提起】 若年妊婦が抱える課題(知識不足、相談しづらい環境、経済的な不安、偏見など)を具体的に述べましょう。
③【自分の考え】 助産師としてどのように関わるべきかを述べます。例えば「まずは話をじっくり聞く」「周囲に相談できる人がいるか確認」「支援情報を伝える」といった対応が求められることを書きます。
④【結論】 信頼できる支援体制の存在が、若年妊婦の精神的な安定や安全な出産・育児に直結することをまとめとして伝えます。
また、「妊娠を継続するか中絶するか」「出産後にどう育てていくか」など、若年妊婦が直面する選択肢の多さにも触れ、その判断を尊重する姿勢を示すと、より深みのある文章になります。
| ●まとめ |
若年妊婦の看護は、医学的なケアだけでなく、心理的・社会的な支援が欠かせません。特に、安心して相談できる環境づくりが支援の第一歩です。
助産師として関わるうえでは、まず妊婦本人の声に耳を傾け、背景にある不安や孤独をしっかりと受け止めることが求められます。 そして、家庭内やパートナーとの関係がうまくいかない場合には、行政やNPOなどの外部支援につなげる役割も担う必要があります。
若年妊婦にとって必要なのは「責められること」ではなく「支えられること」。その視点を持って小論文に取り組むことで、受験生自身の助産師としての資質も伝わる文章になるでしょう。
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール