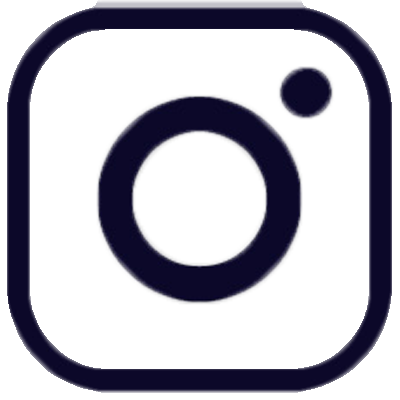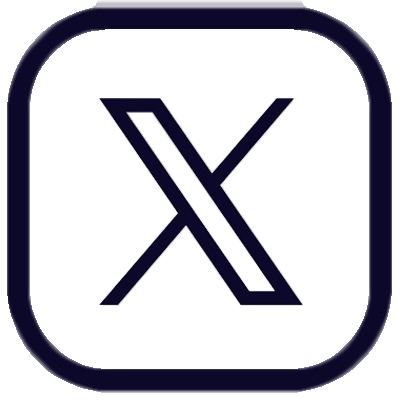お役立ち情報
2025.04.13
助産学校の入試で出た小論文のお題(8)『出生率を上げるにはどうすればよいか(800字)』

助産学校の入試で出た小論文のお題(8)
⁻『出生率を上げるにはどうすればよいか(800字)』
助産学校の入学試験の小論文では、「少子化」や「出生率」に関するテーマが頻繁に出題されています。これらのテーマは、社会全体の課題であると同時に、出産や育児に関わる助産師の立場からも深く関わる重要なトピックです。
今回ご紹介する「出生率を上げるにはどうすればよいか」というお題では、現状を的確に把握した上で、自分なりの考察や提案が求められます。
| ●出生率の現状と地域差 |
日本の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの平均数)は、2023年時点で1.20と、過去最低水準に近い状態が続いており、少子化に歯止めがかかっていないことがうかがえます。さらに、厚生労働省の人口動態統計によると、2024年の出生数は72万988人で過去最低を記録し、これは9年連続の減少となっています。
こうした傾向は全国一律ではなく、地域によって大きな差があります。 たとえば、都道府県別の出生率を見てみると、沖縄県が1.70、宮崎県が1.63と比較的高い一方で、東京都や京都府などの都市部では1.2前後と低く、1.0を下回る地域も存在します。
さらに市区町村別で見ると、鹿児島県大島郡徳之島町が2.25と最も高く、京都府京都市東山区は0.76と最も低いというように、地方と都市部の間で顕著な開きがあります。(※1)
| ●出生率低下の要因 |
少子化の原因としては、晩婚化や非婚化、経済的不安定さ、共働き家庭の増加、子育てにかかる費用と労力、住環境の問題などが挙げられます。また、都市部では待機児童問題や保育環境の不安も大きな要因です。こうした要因が複雑に絡み合い、「子どもを持つことが当たり前ではない社会」が形成されつつあります。
| ●出生率を上げるための対策 |
出生率を上げるためには、経済的支援と社会制度の充実が必要不可欠です。
たとえば、
・出産・育児に対する手当の充実(出産育児一時金、児童手当など)
・保育園・幼稚園の整備、待機児童対策 働きながら子育てができる環境づくり(育休・時短勤務の取得支援)
・住まいや教育に対する支援
また、育児を「大変なこと」としてではなく、「人生の喜び」や「社会的な価値のある営み」として伝える啓発活動も必要です。
助産師としても、妊娠期から育児期にわたって家族を支え、安心して子どもを産み育てられる環境づくりに貢献していくことができます。
| ●出生率低下の社会的な影響 |
出生率の低下は、労働力人口の減少、経済成長の鈍化、社会保障制度の持続困難など、多方面にわたる深刻な影響を及ぼします。将来的に「支える人」と「支えられる人」のバランスが崩れ、社会全体が不安定化することが懸念されています。これはもはや「家庭の問題」ではなく、国家的な課題です。
| ●小論文を書く際のポイント |
このテーマでは、「なぜ出生率が下がっているのか」という分析と、「それをどうすれば改善できるのか」という提案の両方が求められます。一方的な理想論にせず、データに基づいた現実的な視点を持ちつつ、自分の言葉で「これからの社会のあり方」を考察していくことが大切です。
| ●まとめ |
少子化の進行は、医療・教育・経済すべてに関わる重大な社会問題です。助産師を目指す受験生として、「出産・育児を支える立場から何ができるか」を自分の視点でしっかりと書くことが、このテーマのカギになります。
柔軟な発想と現実的な視野を持ち、未来を見据えた文章を目指しましょう。
(※1)厚生労働省 平成 30 年~令和4年 人口動態保健所・市区町村別統計の概況 ![]()
お問い合わせ
Contact
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール